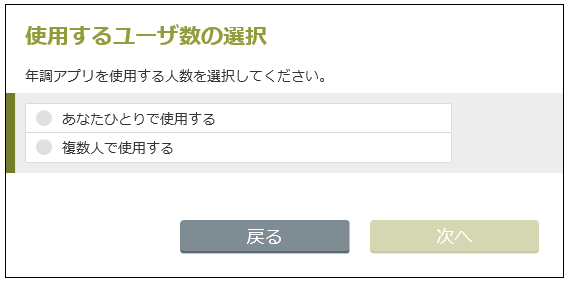国税庁の無料アプリ「年末調整」 操作方法などQ&A
国税庁が提供する無料アプリ「年末調整」の詳しい内容については
次のリンク先をご覧ください。
Q1
国税庁が提供している「年末調整」アプリは
クラウド上にある1つのソフトを、
各従業員が利用するクラウド型でしょうか。
それとも、従業員各自がスマートフォンやパソコンに
ダウンロードするインストール型でしょうか。
A1
社長や従業員の方がお持ちのスマートフォンやパソコンに
ダウンロードして利用する形になりますので、インストール型になります。
入力内容は個人情報の塊です。
クラウド会計屋がやらかすような情報流出の危険を避けるため
クラウド型にしなかったのだと思います。
インストール型の他のメリットとしては
ネット環境によって動きが遅くなったりしません。
サクサク入力できますので、
クラウド会計のようなストレスは溜まりません。
Q&A一覧へ▲
Q2
養う必要がある家族、配偶者がおらず、保険にも加入していません。
住宅ローンもありません。受けられる控除は少ないです。
この場合、最低限、どの書類を作成すれば良いですか?
A2
控除が少ない、最もシンプルな場合は、申告書を3つ作成します。
1.令和7年分扶養控除等(異動)申告書
2.令和8年分扶養控除等(異動)申告書
3.令和7年分基礎控除申告書
アプリの画面では以下のようにチェックが入ります。
Q&A一覧へ▲
Q3
住宅ローン控除を受けるために、アプリに入力しようとしているのですけれども
ややこしいです。このままでは年末調整が終わる気がしません。
A3
経理担当者や会計事務所に相談してみましょう。
分かる範囲まで電子データで入力し、
契約書や登記簿謄本、住宅借入金の年末残高等証明書も一緒に提出し、
経理担当者や会計事務所側は、それを元にして年末調整の処理を進める、
といった対応も考えられます。
厳しい担当者だと、対応してくれない可能性もありますので
早めに相談するのが良いと思います。
税務署の無料電話相談を利用するという方法もあります。
Q&A一覧へ▲
Q4
自分の給与見込額を入力しようと思うのですけれども
「給与収入」と「給与所得」という似たような言葉が並んでします。
何がどう違うんですか?
A4
まず、「収入」と「所得」の違いについて
会社や個人事業主の例を使って説明します。
会社や個人事業主の場合、
売上(収入)-仕入経費=利益(所得)
という計算を行い、利益(所得)に対して税金がかかります。
・収入=売上
・所得=売上から仕入経費を差し引いたもうけ、利益
です。給与をもらうサラリーマンも基本的に同じ考えです。
・給与収入=年間給与額面額=年収
・給与所得=給与収入から経費を差し引いたもうけ
となります。
しかし、
サラリーマンの経費といっても、せいぜいスーツ代や昼食費などしかなく、
ほとんど経費がありません。
このままだと、収入に比べて税金が大きくなり
サラリーマンは不利、不公平になります。
そこで、給与収入の水準に応じた、
ざっくり概算の経費(給与所得控除)を差し引いて良い
というルールになっています。
実際に経費を支払っているかどうかは関係ありません。
支払っていなくても「支払っているとみなす」ということです。
給与収入(年収)-給与所得控除=給与所得
と計算します。
年収400万円の方であれば、
給与収入400-給与所得控除120万円=給与所得280万円
年収800万円の方であれば
給与収入800-給与所得控除190万円=給与所得610万円
というように計算します。
給与収入と給与所得の内容をまとめると
・給与収入=年間給与額面額=年収
・給与所得=給与収入から給与所得控除を差し引いたもうけ
となります。
国税庁の無料アプリ「年末調整」は
給与収入=年収を入力すれば、
給与所得控除および給与所得金額を
自動計算してくれます。
Q&A一覧へ▲
Q5
アプリの中の「計算表」ボタンを押して給与所得を計算しようと思います。
その中で「特定支出」という言葉があります。
数字を入力できるようですけれども、これってなんですか?
A5
上記、Q4のとおり
給与収入(年収)-給与所得控除=給与所得
という計算を行いますけれども、
会社勤務のために自らが負担した、通勤費、研修費、交際費、書籍代などがあれば
「特定支出」として追加で差し引くことができます。
給与収入(年収)-給与所得控除-特定支出=給与所得
というように、
特定支出を追加すれば、給与所得が減り、税金が減ります。
しかし、厳しい条件があります。
実際はほとんど使えません。
条件は以下のとおりです。
①支出額が、給与所得控除の2分の1を超えた場合、その超えた部分を特定支出にできる
②会社から証明書をもらう必要がある
①の条件を具体的な数字で説明します。
年収400万円の方の場合、ざっくり
給与収入400-給与所得控除120万円=給与所得280万円
となります。給与所得控除の2分の1は60万円です。
通勤費や交際費が会社負担であれば、特定支出の対象外です。
それ以外に自己負担した研修費や書籍代が年間80万円あれば
80万円ー60万円=20万円を特定支出として差し引けます。
給与収入400-給与所得控除120万円-特定支出20万円=給与所得260万円
このような計算になりますけれども、実際のところ、
研修費や書籍代等に年間60万円以上もかける方は、なかなかいないと思います。
②の条件である
それが業務に必要だったという証明書を会社からもらうのも
ハードルが高いと思います。会社に責任が生じるからです。
条件を満たすのが難しいため
特定支出を受けられるサラリーマンの方は、ほとんどいないと思います。
アプリの「特定支出」には「ゼロ」と入力してください。
Q&A一覧へ▲
Q6
年末調整アプリをパソコンにインストールしました。
起動した時に、以下のような画面が出てきました。
当社は、従業員が複数おりますので、
「複数人で使用する」を選択すればよろしいのでしょうか。
A6
従業員が複数いることとは関係ありません。
この画面メッセージの意味は
「アプリをインストールしたパソコン1台を、複数人で使用しますか?」
ということです。
そのパソコンで、お1人だけがアプリを使用するのであれば
「あなたひとりで使用する」を選択します。
Q&A一覧へ▲
Q7
国税庁「年末調整」アプリを
ダウンロードサイトから入手しようとしたところ
評価点が低く、厳しいコメントが多いようです。
本当に使っても大丈夫なのでしょうか?
A7
大丈夫です。まったく問題ありません。
当事務所のお客様は、
みなさま、問題なく使用されております。
「うまく動かない」といった不具合の連絡もありません。
評価コメントを見たところ、
・そもそもアプリには関係のない、年末調整の仕組み自体を誤解した意見
・年末調整アプリを有料提供している、民間会社の評価攻撃
がほとんどです。個人的な印象ですけれども。
とくに、年末調整アプリは、多くの民間会社も有料提供しています。
無料の国税庁アプリを使われてしまうと、商売あがったりのため
低評価を連発して評判を落とそうとします。
仕事上、民間会社の有料アプリも使ったことがありますけれども
国税庁アプリの使い勝手、機能は十分です。
民間アプリと大差ありません。
差があるとすれば、
民間アプリは、年末調整結果を
給与計算ソフトや会計ソフトに自動連携できるという点だけです。
連携が不要な場合、有料アプリを使う必要はありません。
連携がお粗末で、別々に入力した方が早いという
意味不明な民間有料ソフトもあります。
無料の国税庁アプリが断然おトクです。
Q&A一覧へ▲
Q8
今年、ふるさと納税を行いました。
所得税と住民税が少なくなり、
税金の還付金も増えると聞いております。
ふるさと納税関係の情報は、
どのようにアプリに入力すればよろしいでしょうか。
A8
ふるさと納税によって
税金は少なくなりますけれども、年末調整とは別に、
ご自身個人で確定申告を行う必要があります。
年末調整とふるさと納税は別々の手続です。
ふるさと納税関係の情報をアプリに入力する必要はありません。
入力画面自体が存在しません。
ふるさと納税関係の証明書類を会社に提出する必要もありません。
年末調整のあと、確定申告で
ふるさと納税の手続処理を行うことによって
追加の還付があります。
年末調整で受け取った源泉徴収票と
ふるさと納税の証明書を元に
e-Taxもしくは税務署等の無料相談を受けながら
確定申告をしましょう。
Q&A一覧へ▲
Q9
年末調整アプリからデータを出力したあと
従業員各自が、クラウド上の会計システムに、それを取り込むよう
会社から指示を受けています。
取り込み方法が良く分かりません。
A9
お勤め先の会社にご確認ください。
このホームページは、
御社と取引関係のない、東京都の会計事務所が
年末調整アプリに関する説明だけを行っております。
各会社の年末調整の方法までは関知しておりません。
当事務所に聞かれても困ります。回答できません。
Q&A一覧へ▲
Q10
年末調整アプリから出力したデータを
スマートフォンに添付する方法が分かりません。
どうもメール送信アプリが起動しないようです…。
スマートフォンの操作方法を教えてくれますか?
A10
教えることは難しいです。
当事務所はスマートフォンメーカーや販売代理店ではないからです。
スマートフォンに添付する方法は、
インターネット上でご自身で調べるか、
御社の年末調整担当者に質問するか、
ご家族や親しい会社の同僚に聞くのが早いでしょう。
それでも解決しない場合は
国税庁のアプリ自体に問題がある可能性があります。
以下のヘルプデスクに
遠慮なく電話して相談しましょう。
【国税庁の年末調整アプリ ヘルプデスク】
0570-02-4563
受付時間:午前9時から午後5時
10⽉1⽇~12⽉28⽇(休祝⽇を含む)
1⽉4⽇~2⽉28⽇(休祝⽇を除く)
画面トップへ▲